2017年04月26日
動物は死後どうなるか(12)
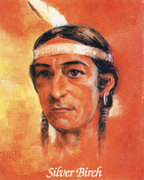
問「犬の次に進化している動物は何ですか。猫ですか猿ですか」
「猫です」
問「なぜ猿ではないのでしょう。人間と非常によく似ていると思うのですが」
「前にも述べましたが、進化というのは一本道ではありません。
かならず優等生と劣等生とがいます。
人間はたしかに猿から進化しましたが、その猿を犬が抜き去ったのです。
その大きな理由は人間が犬を可愛がったからです」
問「犬が人間の次に進化しているから可愛がるのだと思っていましたが・・・・・」
「それもそうですが、同時に人間の側の好き嫌いもあります。
それからこの問題にはもう一つの側面があるのですが、ちょっと説明できません。
長い長い進化の道程において、猿はいわば足をすべらせて後退し、残忍にはならなかったのですが、ケンカっぽく、そして怠けっぽくなって歩みを止めてしまい、結局類魂全体の進化が遅れたのです。
それと同時に、というより、ほぼその時期に相前後して、犬の種属が進化してきました。
猿より類魂全体の団結心が強く、無欲性に富んでいたからです。
しかしどうも話が複雑になりすぎたようです」
問「猿の種属が法則を犯したのでしょうか」
「法則を犯したというのではなく、当然しなければならないことをしなかったということです」
問「では猿と同じように、将来、犬が進化の階段をすべり落ちるということもあり得るのでしょうか」
「それはもう有り得ないでしょう。というのは、すでに何百年もの進化の過程を辿って来て、地上の種がすっかり固定してしまったからです。
種の型がほとんど定型化して、これ以上の変化の生じる可能性はなくなりつつあります。
物質的進化には限度があります。
形体上の細かい変化はあるかも知れませんが、本質的な機能上の変化は考えられません。
細かい変化は生じても、すっかり形体が変わることはありません。
たとえば人間の場合を考えてごらんなさい。
現在の型、すなわち二本の腕と脚、二つの目と一つの鼻が大きく変化することは考えられません。
これが人間の標準の型となったわけです。
もちろん民族により地方によって鼻とか目の形が少しずつ違いますが、型は同じです。
動物の場合はこの傾向がもっと強くて、霊界の類魂に突然変異が発生することはあっても、それが地上の動物の型を大きく変化させることはまずないでしょう」
問「猿の転落もやはり自由意志に関連した問題ですか」
「それは違います。
自由意志は個的存在の問題ですが、動物の場合は類魂全体としての問題だからです」
問「動物に個体としての意識がないのに、なぜ類魂全体としての判断が出来るのですか」
「本能による行動と本能の欠如による行動の違いがあります。
個々には理性的判断力のない動物でも、働くか怠けるかを選ぶ力はあります。
必要性に対して然るべく対処するかしないかの選択です。
そこで種としての本能が伸びたり衰えたりします。
個々には判断力はなくても、長い進化の過程において、種全体として然るべき対処を怠るという時期があるわけです。
問「それは植物の場合にも言えるわけですか」
「言えます」
問「それは外的要因によっても生じるのではないですか」
「それはそうですが、あなたのおっしゃる外的というのは実は内的でもあるのです。
それに加えて更に、霊界からコントロールする霊団の存在も考慮しなくてはいけません。
その霊団もまた法則、進取性、進歩といった要素に支配されます。
問「たとえば猿の好物であるナッツが豊富にあれば、それが猿を怠惰にさせるということが考えられませんか」
「そういうことも考えられますが、ではナッツがなぜ豊富にあったかという点を考えると、そこには宇宙の法則の働きを考慮しなくてはいけません。
つまり人間の目には外的な要因のように見えても、霊界から見れば内的な要因が働いているのです。
私の言わんとしているのはその点なのです。
人間はとかく宇宙の法則を何か生命のない機械的な、融通性のないもののように想像しがちですが、実際は法則と法則との絡まり合いがあり、ある次元の法則が別の次元の法則の支配を受けることもありますし、その根源において完全にして無限なる叡智によって支配監督されているのです。
法則にもまず基本の型というものがあって、それにいろいろとバリエーション(変化)が生じます。
といっても、その基本の型の外に出ることは絶対に出来ません。
どんなに反抗してみたところで、その法のワクはどうしょうにもなく、結局は順応していくほかはありません。
しかし、同じ型の中にあって、努力次第でそれを豊かで意義あるものとしていくことも出来るし、窮屈で味気のないものにしてしまうことも出来ます。
別の言い方をすれば、その法則に調和した色彩を施すのも、あるいはみっともない色彩をぬりつけてしまうのもあなた次第ということです。
いずれにせよ、最後は型に収まります」
Posted by クルト at
09:47
│Comments(0)




